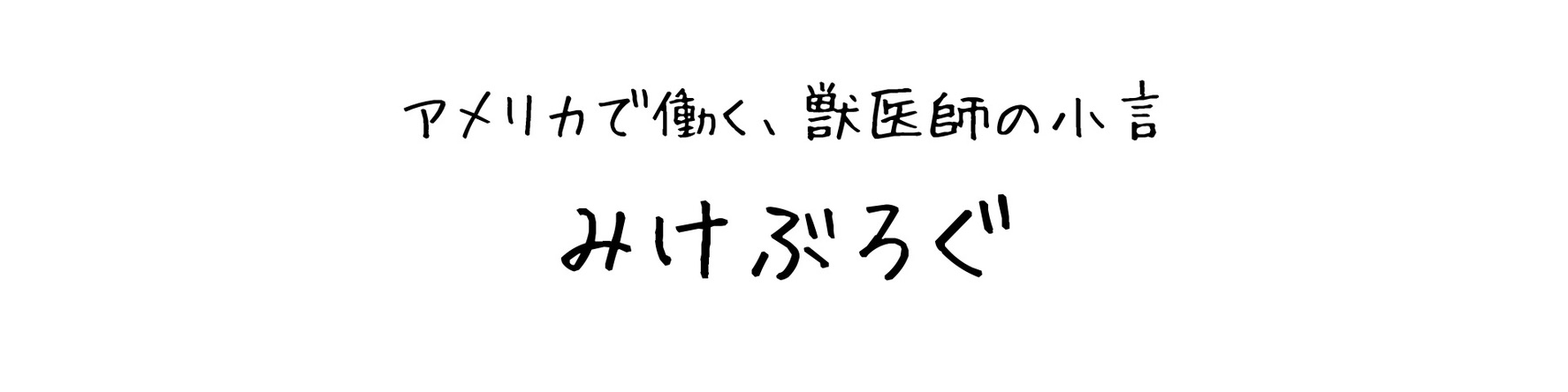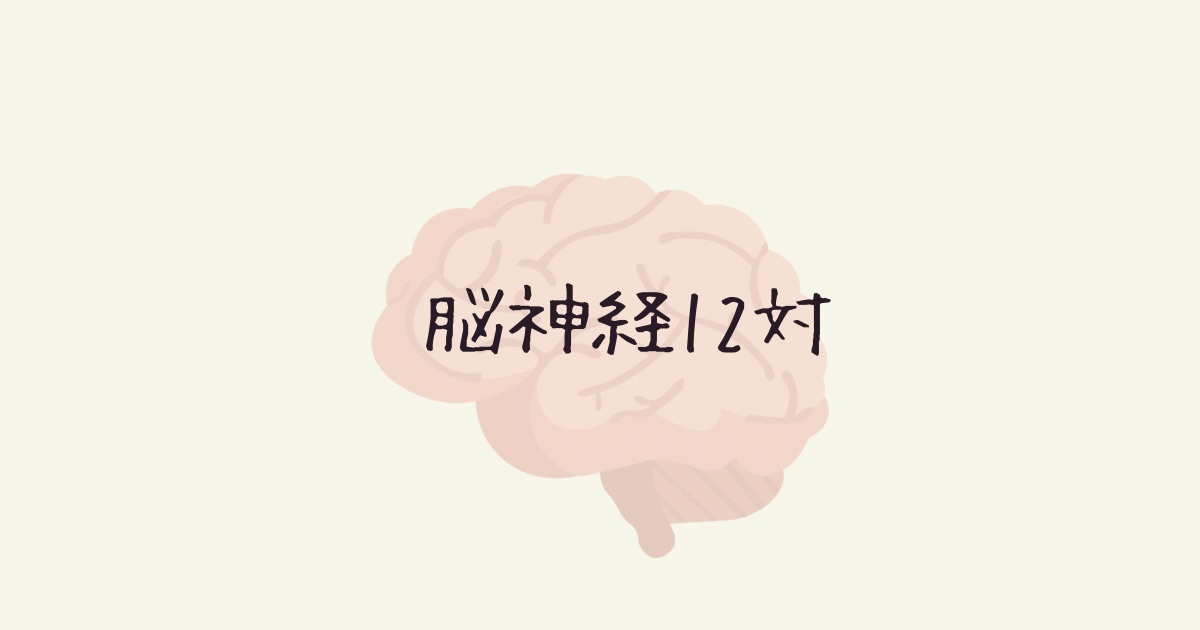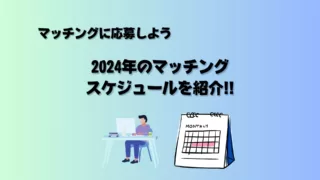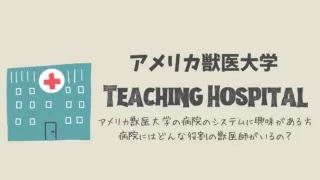この記事の内容
- 脳神経検査とは(前編)
- 1-12対の脳神経(中編)
- 1-12対の脳神経の評価(後編①・②)
著者は、日本の獣医大学を卒業後、一般病院で3年間勤務した後、現在アメリカの大学で獣医研修医をしています。
この記事では、何のために脳神経検査を行うのか、12対の脳神経の機能、さらに12対の脳神経機能を評価する方法をイラストを用いて説明します。前編では、何のために脳神経検査を行うか。神経検査の重要性について理解していただくためにちょっとした症例を交えて解説していきます。
[read_more id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]
脳神経検査とは
脳神経検査は何のために行うか。その名の通り、脳神経に異常がないかを調べるための検査です。
アメリカの学生と症例を見ていると、以下のことに気がつきました。
- 神経科にいるとき、神経検査をある程度できるし、ローカリゼーション(病変部位を推測すること)もできる
- エマージェンシーにいる時。神経症状が主訴で訪れた患者さんに対しては約半分の学生が言わなくても神経検査を始めることができる。
- エマージェンシーにいる時。神経症状が主訴ではない患者さんに対して、必要に応じて神経検査を言わなくてもできる学生は10%以下。
面白いことに、彼らは神経検査のやり方も、評価方法も知っているのに、神経検査を行うべきタイミングを知らないのです。私が学生の頃は、神経検査の適切なやり方さえわかっていなかったので、できること事態素晴らしいとは思いますが、せっかくやり方を知っているのに、実際の臨床現場で使えないのはもったいないですね。
もちろん、発作や明らかな神経症状で来院した患者さんに、神経検査を行い、ローカリゼーションをすることが重要なことは解説なしにもわかっていただけると思います。
では例えば、
- 重度の外耳炎を患う患者さん(猫)が、斜頸を主訴に来院した時
- 前肢跛行を主訴に来院した患者さん
- 後ろ足で背中あたりを無性にかこうとしている患者さん
に対して、神経検査はどの程度必要でしょうか。これらは、実際に私が遭遇した患者さんで、神経科のコンサルテーションを受け、最終的に中枢神経に異常が見つかったという症例です。
外耳炎を伴う患者さんは、神経検査によって斜頸に加え、ホルネル症候群、企図振戦が見つかりました。小脳性の運動失調を呈していることが明らかになり、中枢神経にまで感染が波及していたことが疑われたため、MRIへ進むことが推奨されました。
もともとは、外耳の感染、末梢の前庭症状のみでしたが、神経検査を行うことで中枢神経の関与が明らかになった例です。余談ですが、この猫は非常にストレスを受けやすい猫で、可能な神経検査にも限界がありました。
そこで「中枢神経の波及があるかないか」を判断することをゴールとした、ミニマムな神経検査を行うことで、診断プランを決定することができました。
前肢跛行で来た患者さんですが、飼い主さんは”跛行”と表現していましたが、右前肢のナックリング(固有位置間隔異常の運動失調)、さらにはホルネル症候群、皮筋反射の消失が見つかり、MRIで末梢神経鞘腫が疑われました。
実はこの患者さんに関しては、前の先生から整形のコンサルのリクエストが出されていたのです。ナックリングを伴う歩様を見て、すぐに神経疾患だとわかったので、自分で神経検査をした上で、神経科のコンサルを受けることができたのです。
跛行=整形という凝り固まった頭になってしまうと、神経検査をすることなく違う方向に患者さんを導いてしまう可能性があります。
神経疾患を鑑別として入れられるかがもっとも重要なポイントになります。
後ろ足で背中あたりを無性にかこうとしている患者さんは、神経検査によって小脳性の運動失調が見られ、MRIによってCOMSおよび脊髄空洞症が診断されました。余談ですがこの症状は、ファントムスクラッチという、脊髄空洞症に特異的な症状で、脊髄の違和感からくる異常行動です。
神経検査の目的は、脳神経が障害を受けているか否かを明らかにすることです。上記の3症例でもっとも重要なポイントは、神経の関与を疑えるかどうかが鍵になります。
神経検査をするかしないか。もちろんすべての患者さんに神経検査をすることにすれば、この様な見落としはなくなるはずです。しかし、忙しい臨床現場では、なるべく必要な検査に絞り、的を得た検査に時間をかけるべきです。
ここで重要なのは、繰り返しになりますが、その症状から神経疾患を鑑別に入れられるか?というところになります。
まとめ
- 神経検査のやり方を知っていても、いつ神経検査をするべきか分からなければ意味がない
- この症状から神経疾患を鑑別に入れられるか?がキーポイント
[/read_more]